伊那谷再訪
先日はまるで梅雨のような雨続きにやられ、空振りの取材となってしまいましたが、台風も一過、ようやく晴れの予報が続きましたので再び伊那谷を訪れました。仕事? 仕事・・・・ってなんだっけ。 7日の夕方に大阪を出発、豊橋で一泊して8日朝6:00の飯田線に乗車、天竜峡・飯田で乗り換え、10時過ぎには伊那大島に到着です。18きっぷシーズンの上諏訪・豊橋直通519M列車は混み合いますから、自転車を輪行しての乗車は気を遣います。スケジュールが許すなら、今回のように他の乗り継ぎ列車にするのが良いでしょう。 ▼秋ですね  しばらく涼しい日が続いたからでしょうか、稲穂は黄金色に実り、ススキが丈を伸ばし、秋桜は花を咲かせ、あちらもこちらもすっかり秋めいてきました。風情があって良いものですが、テクスチャ材料としては画像を修正しないと季節感が狂ってしまうので面倒です。 初日の取材は伊那大島~上片桐~伊那田島の3駅間と、飛んで小町屋、駒ヶ根あたりを自転車で廻ってみっちりと。特に伊那大島・上片桐は比較的駅周辺が栄えているため建物も多く、鉄道林で隠れている区間以外は、ほとんど歩いて取材をするのと変わりません。 ▼赤蕎麦
しばらく涼しい日が続いたからでしょうか、稲穂は黄金色に実り、ススキが丈を伸ばし、秋桜は花を咲かせ、あちらもこちらもすっかり秋めいてきました。風情があって良いものですが、テクスチャ材料としては画像を修正しないと季節感が狂ってしまうので面倒です。 初日の取材は伊那大島~上片桐~伊那田島の3駅間と、飛んで小町屋、駒ヶ根あたりを自転車で廻ってみっちりと。特に伊那大島・上片桐は比較的駅周辺が栄えているため建物も多く、鉄道林で隠れている区間以外は、ほとんど歩いて取材をするのと変わりません。 ▼赤蕎麦  上片桐~伊那田島間では伊那谷の名産「高嶺ルビー」と呼ばれる“赤蕎麦”が花を付けておりました。まだ七分咲きといったところですが、一面の赤い絨毯はなかなかの見物。 花だけではなく実も赤く、作った蕎麦も少し赤味を帯びていて香りが高いとのこと。一度食べてみたいのですが、普通の蕎麦に比べると面積あたりの収穫量が1/3程度ということもあり、新蕎麦の季節でないと食すことができません。だいたい9月下旬から10月上旬でしょうか、いずれは機会を作りたいですね。 ▼みや川
上片桐~伊那田島間では伊那谷の名産「高嶺ルビー」と呼ばれる“赤蕎麦”が花を付けておりました。まだ七分咲きといったところですが、一面の赤い絨毯はなかなかの見物。 花だけではなく実も赤く、作った蕎麦も少し赤味を帯びていて香りが高いとのこと。一度食べてみたいのですが、普通の蕎麦に比べると面積あたりの収穫量が1/3程度ということもあり、新蕎麦の季節でないと食すことができません。だいたい9月下旬から10月上旬でしょうか、いずれは機会を作りたいですね。 ▼みや川  晩飯は何度も登場しています伊那市の「みや川」にて。地のモノでも何でもない「ハンバーグ定食」ですが、昼食を抜いた上、1日中自転車に乗っていたので空腹に耐えかねて、つい・・・。 写真ではわかりませんが、ハンバーグは長さ15センチ、厚みが3~4センチくらいの巨大なもの。ご飯を小にしましたが(通常だとドンブリに山盛り)それでも終盤はフードファイト状態に。 これでお値段580円→ご飯小で50円引きの530円です。とにかく安くで腹一杯になりたい時はココですね。 宿泊は南箕輪、木ノ下~北殿間の漫喫に連泊です。 ▼温泉
晩飯は何度も登場しています伊那市の「みや川」にて。地のモノでも何でもない「ハンバーグ定食」ですが、昼食を抜いた上、1日中自転車に乗っていたので空腹に耐えかねて、つい・・・。 写真ではわかりませんが、ハンバーグは長さ15センチ、厚みが3~4センチくらいの巨大なもの。ご飯を小にしましたが(通常だとドンブリに山盛り)それでも終盤はフードファイト状態に。 これでお値段580円→ご飯小で50円引きの530円です。とにかく安くで腹一杯になりたい時はココですね。 宿泊は南箕輪、木ノ下~北殿間の漫喫に連泊です。 ▼温泉  9日は駒ヶ根~沢渡間を線路沿いに取材。朝夕は日光の黄味と影が強すぎて良い写真が撮れないため、実質的に活動できるのは10~15時くらいに限られてしまいます。曇天なら早朝~日没まで、それなりに使える写真が撮れるのですが、まぁあまり贅沢を言って雨に降られては困りますので、我慢しましょう。 なんとか満足のいく写真素材を撮り集め、早めに活動を切り上げて伊那市の「みはらしの湯」でマッタリしてきました。伊那市の中心部から約7kmとお手軽な距離ですが、中央アルプスの裾野、標高900m(伊那市駅からの標高差は約260m)の高台にありますので、ずっと上り坂です。体力・脚力が十分ではありませんのでかなりキツイ行程ですが、汗だく→温泉の爽快感はたまりません。 露天風呂や休憩室からは伊那谷と南アルプスが一望でき、黄昏時から夜景への移ろいを風呂からボ~ッと眺めるのは、なんとも贅沢な時間の使い方ですね。 ▼サイクリング
9日は駒ヶ根~沢渡間を線路沿いに取材。朝夕は日光の黄味と影が強すぎて良い写真が撮れないため、実質的に活動できるのは10~15時くらいに限られてしまいます。曇天なら早朝~日没まで、それなりに使える写真が撮れるのですが、まぁあまり贅沢を言って雨に降られては困りますので、我慢しましょう。 なんとか満足のいく写真素材を撮り集め、早めに活動を切り上げて伊那市の「みはらしの湯」でマッタリしてきました。伊那市の中心部から約7kmとお手軽な距離ですが、中央アルプスの裾野、標高900m(伊那市駅からの標高差は約260m)の高台にありますので、ずっと上り坂です。体力・脚力が十分ではありませんのでかなりキツイ行程ですが、汗だく→温泉の爽快感はたまりません。 露天風呂や休憩室からは伊那谷と南アルプスが一望でき、黄昏時から夜景への移ろいを風呂からボ~ッと眺めるのは、なんとも贅沢な時間の使い方ですね。 ▼サイクリング  10日は18きっぷの最終日。この日のうちに帰阪しないといけませんが、七久保で撮りたいものがあったので、朝から自転車で南下。伊那市街の一部を除いて国道153号の路側帯が狭く、しかも大型車がやたら多いのは前の2日間でよくわかりましたので、天竜川左岸の県道18号を走行。比較的直線・平坦な右岸の国道153号とは打って変わっての田舎道で、伊那・駒ヶ根市境の「火山峠(ひやまとうげ)」をはじめ、常にアップダウンの繰り返しになります。 国道より時間はかかりますが交通量が少なく安全で、なにより左に南アルプス、右に天竜川と中央アルプス、周囲には森や田圃と最高のロケーション。観光で伊那谷を訪れる方は、是非とも国道ではなくこちらを満喫して欲しいですね。ただし松川町内には離合不能な区間が多数ありますので、自動車の場合、運転に自信のない方は要注意です。 同ルートは自転車の練習コースになっているのか、短い間に5人のロード乗りとすれ違いました。お互いメットを下げてご挨拶。中には交流を嫌う方もいらっしゃるでしょうが、同じ趣味の方とすれ違うと、上り坂の途中でも「もうちょっと頑張ろう」という気になります。 飯島町に入って天竜川右岸へ移り七久保駅へ。駅周辺で数カット撮影して自転車での取材は完了です。この3日間で合計160kmほど走りましたが、乗って降りて撮っての繰り返しの割には、よく走れた方です。 午前のうちに上諏訪発の豊橋直行に乗車、快適な313系ですから、そのまま乗っていても良かったのですが、中部天竜の旧貨物ホーム上屋を撮っておきたかったので下車し、1本遅らせて119系でガタゴト豊橋へ。あとは新快速乗り継ぎで、米原で乗り換えるだけの楽チンなタイミングでした。 紆余曲折ありましたが、なんとか冬の間も作業の手を止めないで済むくらいの素材が集まりました。路線データはこの調子で進めるとして、車両さえ何とかなればという条件付きですが、来年中の部分公開も可能ではないかと思います(もちろん確約ではありませんよ、念のため)。 タイミング的に119系引退で飯田線が賑わってくる頃でしょうが、逆に言えば車両の音素材などは、今冬中に収録しておかなければなりませんね。リニアPCMのICレコーダも随分と安くなりましたし、頑張って買っちゃいましょうか。自転車での取材で重いデジ一眼を持ち歩くのはキツイので、マシなコンデジも欲しいし、なんだかんだで出費が続きそうです。
10日は18きっぷの最終日。この日のうちに帰阪しないといけませんが、七久保で撮りたいものがあったので、朝から自転車で南下。伊那市街の一部を除いて国道153号の路側帯が狭く、しかも大型車がやたら多いのは前の2日間でよくわかりましたので、天竜川左岸の県道18号を走行。比較的直線・平坦な右岸の国道153号とは打って変わっての田舎道で、伊那・駒ヶ根市境の「火山峠(ひやまとうげ)」をはじめ、常にアップダウンの繰り返しになります。 国道より時間はかかりますが交通量が少なく安全で、なにより左に南アルプス、右に天竜川と中央アルプス、周囲には森や田圃と最高のロケーション。観光で伊那谷を訪れる方は、是非とも国道ではなくこちらを満喫して欲しいですね。ただし松川町内には離合不能な区間が多数ありますので、自動車の場合、運転に自信のない方は要注意です。 同ルートは自転車の練習コースになっているのか、短い間に5人のロード乗りとすれ違いました。お互いメットを下げてご挨拶。中には交流を嫌う方もいらっしゃるでしょうが、同じ趣味の方とすれ違うと、上り坂の途中でも「もうちょっと頑張ろう」という気になります。 飯島町に入って天竜川右岸へ移り七久保駅へ。駅周辺で数カット撮影して自転車での取材は完了です。この3日間で合計160kmほど走りましたが、乗って降りて撮っての繰り返しの割には、よく走れた方です。 午前のうちに上諏訪発の豊橋直行に乗車、快適な313系ですから、そのまま乗っていても良かったのですが、中部天竜の旧貨物ホーム上屋を撮っておきたかったので下車し、1本遅らせて119系でガタゴト豊橋へ。あとは新快速乗り継ぎで、米原で乗り換えるだけの楽チンなタイミングでした。 紆余曲折ありましたが、なんとか冬の間も作業の手を止めないで済むくらいの素材が集まりました。路線データはこの調子で進めるとして、車両さえ何とかなればという条件付きですが、来年中の部分公開も可能ではないかと思います(もちろん確約ではありませんよ、念のため)。 タイミング的に119系引退で飯田線が賑わってくる頃でしょうが、逆に言えば車両の音素材などは、今冬中に収録しておかなければなりませんね。リニアPCMのICレコーダも随分と安くなりましたし、頑張って買っちゃいましょうか。自転車での取材で重いデジ一眼を持ち歩くのはキツイので、マシなコンデジも欲しいし、なんだかんだで出費が続きそうです。









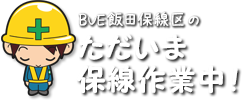






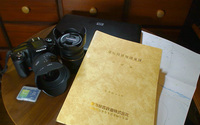

 クリーム色のファイルは運転関係線路要図。平成18年に発行されたものなのでデータが想定している時期とは変わっているところもありますが、そのへんは別資料で補うしかありません。貴重なものなのでまず全ページをコピーして・・・と思っていたのですが、面倒になってそのまま持ち歩いています。まぁコレクターじゃないので、いいか。 勾配や曲線はもちろん、信号機の配置や踏切名なども記載されているので路線データを作る際には重宝しています。ただし、基本的に100m単位で描かれた図ですから、これだけで路線データを作るのは難しいでしょう。現地で得た資料と線路図、地図などを組み合わせて25m単位、そして更に細かなデータを作っていきます。 ■その他雑感 図書館へ寄る時間が取れるか微妙だったのですが、皮肉なことに最終日の炎天下に負けまして、撮影を中断して飯島町の図書館へ避難しました。こぢんまりとした規模で蔵書も多くはありませんが、さすがに郷土史は充実していたので楽しませていただきました。 直接資料になるような記事・写真はほとんど無かったのですが、伊那電が開通した当初の写真を多数見ることが出来、また建築様式と地場産業の関連についての記述も興味深かったですね。ネット全盛の現代ですが、それでも紙メディアの持つ説得力も捨てがたいもので、今まで知らなかったことを知る機会であるのはもちろん、「こうなんじゃないかな?」という推論の裏付けを得る機会にもなります。 今回は飯島町だけでしたが、また次の機会に駒ヶ根市、伊那市の図書館も訪れてみようと思います。 取材期間中は毎晩温泉に入っていたのですが、伊那市の三セクが運営する「みはらしの湯」がそこそこお気に入り。循環させているので塩素臭があるのは残念ですが、ヌルヌル感のある泉質は温泉らしさも十分で、湯上後も気持ちよく過ごせました。 特筆すべきは露天風呂。湯船は小さいものの眺望は良好で、駒ヶ岳山麓に位置するため手前に伊那谷、遥か前方には南アルプスを望むという好立地。露天風呂が好きであちこち入りにいってるんですが、周囲の塀や目隠しのせいで折角の開放感が台無しになっているところが多い中、ここは高台にあるので目隠しも低く、半身浴したまま景色を眺められるのが良いですね。また先述の塩素臭も風がさらってくれるので気になりません。 スケジュールを合わせたわけではなく偶然だったのですが、7/31は『みのわ祭り』の花火大会が行われ、露天風呂に入りながら暮れゆく空と打ち上げ花火を眺めるという、最高に贅沢なシチュエーションを堪能させていただきました。会場は伊那市のお隣の箕輪町、駅で言えば伊那松島のあたりですので距離が8kmほどあり、眼前に広がる大迫力・・・とはいきませんが、人混みに押されることもなくゆったりと、なんとも風情あふれる一時でした。 ちょうど帰阪した頃から100歳以上の高齢者が多数行方不明・・・という悲しいニュースが流れていますが、伊那谷では人々の距離が都市部よりも少し近く、ほっこりさせられました。 人口密度は都市部と比べて圧倒的に低いわけですが、それでも撮影していると農作業をされている方や散歩中の方、結構な数の人と顔を合わせるので、目が合っちゃうとお邪魔している立場のこちらとしてはそのまま逸らすのも気不味いですし、不審者扱いされても困りますので軽く会釈しておいたのですが、そうするとほとんどの方が「こんにちは」と声をかけて返して下さるんですよね。すれ違う子供達なんて向こうから「おはようございまーす!」なんて元気に挨拶してくれて、つい唖然として挨拶を返し損ねそうになったりも。 最初はビックリしましたし、私よりもっと若い方だと「面倒くさい」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、4日も現地に密着しているとだんだん自然に挨拶ができるようになるもので、「あ~、こういうのもいいなぁ」なんて思ってしまいました。まぁ防犯の意味もあるかもしれませんが、少なくとも不快に感じることはありませんから、こういう習慣は素晴らしいですね。
クリーム色のファイルは運転関係線路要図。平成18年に発行されたものなのでデータが想定している時期とは変わっているところもありますが、そのへんは別資料で補うしかありません。貴重なものなのでまず全ページをコピーして・・・と思っていたのですが、面倒になってそのまま持ち歩いています。まぁコレクターじゃないので、いいか。 勾配や曲線はもちろん、信号機の配置や踏切名なども記載されているので路線データを作る際には重宝しています。ただし、基本的に100m単位で描かれた図ですから、これだけで路線データを作るのは難しいでしょう。現地で得た資料と線路図、地図などを組み合わせて25m単位、そして更に細かなデータを作っていきます。 ■その他雑感 図書館へ寄る時間が取れるか微妙だったのですが、皮肉なことに最終日の炎天下に負けまして、撮影を中断して飯島町の図書館へ避難しました。こぢんまりとした規模で蔵書も多くはありませんが、さすがに郷土史は充実していたので楽しませていただきました。 直接資料になるような記事・写真はほとんど無かったのですが、伊那電が開通した当初の写真を多数見ることが出来、また建築様式と地場産業の関連についての記述も興味深かったですね。ネット全盛の現代ですが、それでも紙メディアの持つ説得力も捨てがたいもので、今まで知らなかったことを知る機会であるのはもちろん、「こうなんじゃないかな?」という推論の裏付けを得る機会にもなります。 今回は飯島町だけでしたが、また次の機会に駒ヶ根市、伊那市の図書館も訪れてみようと思います。 取材期間中は毎晩温泉に入っていたのですが、伊那市の三セクが運営する「みはらしの湯」がそこそこお気に入り。循環させているので塩素臭があるのは残念ですが、ヌルヌル感のある泉質は温泉らしさも十分で、湯上後も気持ちよく過ごせました。 特筆すべきは露天風呂。湯船は小さいものの眺望は良好で、駒ヶ岳山麓に位置するため手前に伊那谷、遥か前方には南アルプスを望むという好立地。露天風呂が好きであちこち入りにいってるんですが、周囲の塀や目隠しのせいで折角の開放感が台無しになっているところが多い中、ここは高台にあるので目隠しも低く、半身浴したまま景色を眺められるのが良いですね。また先述の塩素臭も風がさらってくれるので気になりません。 スケジュールを合わせたわけではなく偶然だったのですが、7/31は『みのわ祭り』の花火大会が行われ、露天風呂に入りながら暮れゆく空と打ち上げ花火を眺めるという、最高に贅沢なシチュエーションを堪能させていただきました。会場は伊那市のお隣の箕輪町、駅で言えば伊那松島のあたりですので距離が8kmほどあり、眼前に広がる大迫力・・・とはいきませんが、人混みに押されることもなくゆったりと、なんとも風情あふれる一時でした。 ちょうど帰阪した頃から100歳以上の高齢者が多数行方不明・・・という悲しいニュースが流れていますが、伊那谷では人々の距離が都市部よりも少し近く、ほっこりさせられました。 人口密度は都市部と比べて圧倒的に低いわけですが、それでも撮影していると農作業をされている方や散歩中の方、結構な数の人と顔を合わせるので、目が合っちゃうとお邪魔している立場のこちらとしてはそのまま逸らすのも気不味いですし、不審者扱いされても困りますので軽く会釈しておいたのですが、そうするとほとんどの方が「こんにちは」と声をかけて返して下さるんですよね。すれ違う子供達なんて向こうから「おはようございまーす!」なんて元気に挨拶してくれて、つい唖然として挨拶を返し損ねそうになったりも。 最初はビックリしましたし、私よりもっと若い方だと「面倒くさい」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、4日も現地に密着しているとだんだん自然に挨拶ができるようになるもので、「あ~、こういうのもいいなぁ」なんて思ってしまいました。まぁ防犯の意味もあるかもしれませんが、少なくとも不快に感じることはありませんから、こういう習慣は素晴らしいですね。
