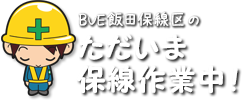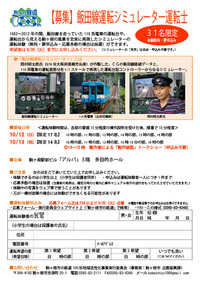2016年Bve大阪運転オフ会
- 2016/04/24 01:08
- カテゴリー:運転会・オフ会
- タグ:Bve大阪運転オフ会
 今年も「Bve大阪運転オフ会」の参加申し込み受付が始まりました。2012年に大阪市内、中崎町の小さなテナントビルの空き部屋を借りて始めたこの催しもアッという間に第五回、今や50畳の広間に70人のBveユーザーが集まる規模にまでなりました。 そもそもの起こりは、作者とプレイヤー、ベテランとビギナー、そういう暗黙の区分のせいでネット上の交流が絶たれていたBveユーザーを混ぜこぜにして、一箇所で楽しく遊べる場を作りたいということでした。 いわゆる飲み会スタイルのオフ会だと、どうしても話題が制作に偏りがちですし、常連の輪の中に新規参加の方が飛び込んでいくのはなかなかハードルが高いものです。 その点、運転台があれば運転するだけでも楽しめますし、人の運転を見ながらワイワイやっているうちに気の合うプレイヤー仲間が見つかることもあります。制作側もPCを持ち込んで技術交換などをしていると、プレイヤーから見た制作の苦労、作者から見たプレイヤーの楽しみ方、双方見えてくるもので、会場の雰囲気を見ていると成果はそれなりに表れているように思います。 大規模になった今では委員会の皆さんに運営していただき、私はあくまでスタッフの一員として参加、発言しているこの会ですが、こうした当初の方針は堅持するようお願いしていますので、初めての方、プレイ専門の方もお気軽にご参加ください。 もうひとつ、私自身がモノを「作るのが好き」なだけで、作った後のことは考えていないというか、むしろ完成が見えてくると飽きてくるタイプなので、皆さんに使って遊んでもらう機会が定期的にあればモチベーションの維持にもなりますし、次回に向けて拡張・グレードアップの繰り返しで終わりのない遊びを続けることができるのです。 そんなわけで持ちつ持たれつ、今年も気合を入れて参加者の皆さまをお待ちしています。お申し込みは運営委員会のページから。お陰様で既に多くの方に申し込みいただいていますので、検討中の方はお急ぎ下さいね!
今年も「Bve大阪運転オフ会」の参加申し込み受付が始まりました。2012年に大阪市内、中崎町の小さなテナントビルの空き部屋を借りて始めたこの催しもアッという間に第五回、今や50畳の広間に70人のBveユーザーが集まる規模にまでなりました。 そもそもの起こりは、作者とプレイヤー、ベテランとビギナー、そういう暗黙の区分のせいでネット上の交流が絶たれていたBveユーザーを混ぜこぜにして、一箇所で楽しく遊べる場を作りたいということでした。 いわゆる飲み会スタイルのオフ会だと、どうしても話題が制作に偏りがちですし、常連の輪の中に新規参加の方が飛び込んでいくのはなかなかハードルが高いものです。 その点、運転台があれば運転するだけでも楽しめますし、人の運転を見ながらワイワイやっているうちに気の合うプレイヤー仲間が見つかることもあります。制作側もPCを持ち込んで技術交換などをしていると、プレイヤーから見た制作の苦労、作者から見たプレイヤーの楽しみ方、双方見えてくるもので、会場の雰囲気を見ていると成果はそれなりに表れているように思います。 大規模になった今では委員会の皆さんに運営していただき、私はあくまでスタッフの一員として参加、発言しているこの会ですが、こうした当初の方針は堅持するようお願いしていますので、初めての方、プレイ専門の方もお気軽にご参加ください。 もうひとつ、私自身がモノを「作るのが好き」なだけで、作った後のことは考えていないというか、むしろ完成が見えてくると飽きてくるタイプなので、皆さんに使って遊んでもらう機会が定期的にあればモチベーションの維持にもなりますし、次回に向けて拡張・グレードアップの繰り返しで終わりのない遊びを続けることができるのです。 そんなわけで持ちつ持たれつ、今年も気合を入れて参加者の皆さまをお待ちしています。お申し込みは運営委員会のページから。お陰様で既に多くの方に申し込みいただいていますので、検討中の方はお急ぎ下さいね!